ハリウッドで活躍してきたチャーリー・シーンといえば、人気・実力を兼ね備えながら、2011年には主演していた人気コメディドラマ『ハーパー★ボーイズ』で問題行動を繰り返して解雇されるなど、たびたびゴシップ記事を賑わせてきた。現在58歳となったチャーリーが、同作クリエイターのチャック・ロリーが手掛ける新作ドラマ『Bookie(原題)』で再タッグを組んだことは以前当サイトでもお伝えした通り。名優マーティン・シーン(『地獄の黙示録』『ザ・ホワイトハウス』)を父親に持ち、兄のエミリオ・エステヴェス(『アウトサイダー』『飛べないアヒル』)とともに自身も若い頃から俳優として活動してきたチャーリーが、米Deadlineのインタビューで自身の整形手術やキャリアについて赤裸々に語った。
-

『ハーパー★ボーイズ』クリエイター、訴訟にまで発展したチャーリー・シーンとの再タッグを語る
かつて人気コメディドラマ『ハーパー★ボーイズ』を解雇されたチ …
解雇騒動を乗り越えて…

2008年2月、『ハーパー★ボーイズ』の共演者ジョン・クライヤー、アンガス・T・ジョーンズと
――チャック・ロリーから復帰を頼まれた時、素直にイエスと答えることができたのですか?
すんなりOKしたよ。彼は面白い演出を思いついたんだ。劇中での私はリハビリ施設に通っているが、患者としてではなく、会員なのでゲームのために部屋を使えるというね。そこで私がカードゲームを提案したところ、彼はそのパイロットエピソードを(『ハーバー★ボーイズ』でジェイクを演じた)アンガス(・T・ジョーンズ)もカメオで登場する『ハーパー★ボーイズ』のカードゲームへのオマージュに変更してくれた。当時の撮影から20年近く経っての出来事だったんだ。
――『ハーパー★ボーイズ』はあなたさえ乗り気なら、あなた主演で10年でも続けられた気がします(※チャーリーがシーズン9途中で降板した後、番組はアシュトン・カッチャーが後釜に座る形でシーズン12まで続いた)。
ああ、私がすべてを台無しにしなければ、望む限りいくらでもやれただろうね。でも、“後悔しながら生きてはいけない”と言うよね。そこから学ばないと…。
-

チャーリー・シーンの後釜はアシュトン・カッチャーじゃなくてヒュー・グラントの予定だった!
『ザット'70sショー』やNetflixの『The Ranch ザ・ランチ』で知られるアシュトン・カッチャー。彼が出演したシットコムシリーズ『ハーパー★ボーイズ』で、2003年の番組開始当初から主演を務めていたのはハリウッドのお騒がせ男チャーリー・シーン。度重なる問題行動の末、本作をクビになったチャーリーに代わり201…
――今振り返ってみて、『ハーパー★ボーイズ』は素晴らしい思い出ですか? それとも、どうしてこんなことに…と思いますか?
素晴らしい思い出ばかりだよ。あの番組がうまくいっている時、視聴者が面白いと思ってくれるものを作り出していた。適当な仕事は誰もしていなかった。全員が本当に懸命に働いていた。みんなだ。自分たちが持っているものの価値、時間をかけてきちんと作ることの価値を知っていた。
私は初日からルールを分かっていた。この職場に貢献するために私に求められていたこと、私に期待されていたことに関するルールだけだけどね。私がそれらと衝突し始めても、ルールが変わることはなかった。まるでスポーツようだったよ。一週間練習して、金曜日の夜には試合(本番収録)があって、ジャージの背中に書かれた名前(自分)ではなくて前に書かれた名前(チーム)のためにプレーするんだ。それを続けるうち私はいつしか、ルールはもう自分には適用されないと思うようになった。うまくいっていたシステムに対して私の言動はフェアではなかったね。
――正直なところ、『ハーパー★ボーイズ』後半の方のエピソードでは、あなたの顔つきが変わり、次第にやつれているのが見て取れます。
何度か助けを求めて良くなったこともあったが、次第に続けていけなくなってしまった。そして私は誰かのせいにしようとした。でも、それはチャックに対しても番組に対してもフェアじゃない。あの番組に出演していた間に2度の離婚を経験し、4人の子どもをもうけた。私生活ではいろいろあったよ。そんなことはステージには持ち込んではいけないんだが、持ち込まないようにするのはどうにも難しい。私がリハビリ施設にいたのはたしかシーズン7を撮り終えた時で、マネージャーとエージェントから契約更新の電話がかかってきた。私は「もう限界かもしれない」と言ったが、周りは「いやいや、まだ物語は続くから」と言う。結局彼らの意図することは、私が続ける限り彼らにお金が入ってくるってことだったんだ。
――そのシーズンのあなたのギャラは一話あたり180万ドル(約2億5000万円)かそれ以上と報じられていましたが…。
たしかに大金だった。でも私は「もうダメだと思うよ」と言ったんだ。直感的に、番組に戻ったらとんでもないことになると思ったから。でも彼らは、「とはいえ、チャーリーは完璧にやり遂げられるだろう」という感じだった。それで新しい契約を結んで、みんな喜んでいたけど、結局すべてが酷いことになった。すべてが最悪だった。
――『ハーパー★ボーイズ』に出演する数年前、健康上の理由により降板したマイケル・J・フォックスの後任を務めた『スピン・シティ』でのあなたはいつもお茶目な悪ガキのように光っていました。シットコムというフォーマットに自分がすぐに馴染んだことは驚きでしたか?
エンターテインメントとして、本当に夢中になって子どもの頃から見てきたものだからね。シットコムはとても心地良かった。シットコムではいつでも同じ人々が同じ環境で、架空の人生を歩もうとしている姿を見ることができ、その番組を通して自分の人生とつながるものを見出すことができた。私の子ども時代の一部だったんだ。
ただ、ようやくシットコムの仕事をする機会に巡り会えた時は、恐ろしかった。(1996年に)『フレンズ』の1エピソードに出たけど、あれは本当に長い1週間だった。でも撮影が終わった時、ショーランナーからキャスト、観客に至るまで、みんなが素晴らしかったことを覚えている。素晴らしい夜だった。“やれたからもういいや”とも思ったけどね。

『フレンズ』でのチャーリー・シーン
――シットコムはドラマより難しいものですか?
私は舞台ものをやったことがなかったから、シットコムをやるまで、観客と交流したり、観客を物語の一部にさせるという感覚をそれまで味わったことがなかったんだ。
――とはいえ、『フレンズ』のエピソードは、1986年の戦争映画『プラトーン』のようなハードな作品を経験してきたことに比べれば、何でもないことのように思えますが?
あれも大変だったけど、これは隠れる場所がないから居心地が悪かった。少なくとも『プラトーン』では、狐穴や木の陰といった隠れる場所をいつでも見つけることができた。映画作りでは、20回もリハーサルをやって、いよいよ本番となる。でもシットコムでは、照明が落ちてベルが鳴ったら…呼吸を整えて落ち着いて、とにかくやるしかないんだ。最初の出番で3行話しただけで、その夜全体がどうなるのか、自分が波に乗っているのか、その波の一部になれているのか、それともただ命がけで泳いでいるのか、だいたい分かるんだ。『スピン・シティ』にレギュラーとして出演することでそれを理解することができた。『スピン・シティ』は、自分の責任が明確で、作品の邪魔をせず、自分の役割を理解している限りは、観客と心地良く接することができる、そんな体験ができる絶好の機会だったと思う。私はいつも何かの支えであることが好きだし、幸運なことに、私のために(脚本を)書いてくれた人たちは、それを私の長所として見てくれた。
――『ハーパー★ボーイズ』であなたが演じたチャーリー・ハーパーは機能不全に陥った支えでしたね…。
海を漂ってしまう錨(いかり)のように頼りない支えだった。でも、最高のチームメイトとも言うべき共演者に恵まれた。ジョン・クライヤー(アラン・ハーパー役)と共演し、ジョンがやっていることに乗っかって演じるのは、魔法のような体験だった。この作品に出演するためにジョンがオーディションを受けると聞いた私は、「でも彼には数十年のキャリアがある。自分たちの相性が知りたいのなら、(チャーリーとジョンが共演した1991年の映画)『ホット・ショット』を見てください」と言ったんだ。チャックとジョンと私の3人で、初めて冷や冷やしながらシーンを演じたんだけど、あれがいわゆる”その瞬間“だったと思う。私もチャックも感じたし、ジョンもそれを感じたと思う。
――それはどんなシーンでしたか?
リビングルームで階段にいた私がスピーチをして、彼は自分の原稿を持っていることを話した時だと思う。序盤で、この男たちがどんな人物かを決定づけたシーンだった。
――何が特別だったのですか?
事前に何も打ち合わせしていなかったのに、最初の読み合わせをしただけで、最高だと分かったんだ。その後チャックに作品のタイトルは決まっているのかと尋ねたら、「『Two and a Half Men(原題)』にしようと思っている」と言われたので、「ヒットしそうだね」と返した。そういう不思議な瞬間があったんだよ。
今回チャックと再び仕事をしたことで、何がいけなかったのか、自分がどれだけのダメージを周りに与えたのかを考えなくて済むようになった。まるでリハビリ治療のようだったよ。一生自分を責め続けるのか? いや、それでは前に進めない。皆の質問に答えられたらいいんだけど、何があったのか分からない。本当に分からないんだ。
無名時代のトム・クルーズやショーン・ペンと交流
――2023年10月にマシュー・ペリー(『フレンズ』)が亡くなった時、ショーン・ペンが「闘病生活で身体を壊したのは残念だ」というようなことを言っていました。あなたがそのような状態から抜け出せて良かったです。
私だけでなくマシュー自身もそこから抜け出したんだ。彼が死んだ時にも似たようなことを感じたよ。本当に悲しかった。6週間ほど前、彼の本(自伝)を一日で読んだんだ。携帯電話の電源を切ってね。瞬時に理解できて、引き込まれるような内容だったから、一気に読みたいと思ったんだ。
――なぜ、それほどまでに引き込まれたのですか?
共感できる部分が多かったから。読みながら、彼と一緒に追体験したんだ。葛藤、執着。分かれ道に立った時、76の魅力的な選択肢ではなく、77番目の選択肢を選ぶ。そうした記述が心に響いた。アルコール依存に苦しむ者同士が集まる会合を通して彼とは少し知り合いだったが、とても素敵な人だった。頭が良くて面白くて魅力的で、いつも自分のことばかり考えているような人間じゃなかった。もっと彼を知りたかった。私が彼の変化に影響を与えることができたとか、何らかの形で彼を助けることができたとは言わないけど、彼をもっと知っていたかったよ。
――昔、人生を立て直そうとしていた頃のロバート・ダウニー・Jr(『アイアンマン』)がプレイボーイ誌のインタビューに答えていたのを覚えています。その中で、彼はあなたの仲間だと言っていましたが、あなたの映画制作グループの一員だったのですか?
『オッペンハイマー』はまだ見ていないけど、彼の演技は見事らしいね。私たちは同じ高校だったけど、彼は私たちが設立したホームムービーのグループには入っていなかった。あそこに所属していたのは、ショーンとクリス・ペン、ロブとチャド・ロウ、そして兄のエミリオと私という3組の兄弟だった。
――あなた方は全員、親がハリウッドの映画業界にいましたが、昔からこの業界に進むことを考えていたのですか?
いや、私たちはスーパー8フィルムを作っていて、(チャーリーより5歳上の)ショーンが最初に卒業したんだ。オーディションを受けた彼は、あっという間にたくさんの仕事をするようになって、『初体験/リッジモント・ハイ』(1982年)や『バッド・ボーイズ』(1983年)が公開され、ドカンと売れたんだよ。
――みんな、自分たちが次代を担う世代だと考えていたのですか?
いやいや、ただ楽しんでいただけだよ。親のやっていることを見よう見まねでやっていたんだ。父と一緒に世界中の撮影現場で育った兄と私は、田舎を撮ればいいと言って両親からスーパー8カメラを渡された。だけど伝えたいものがあった私たちは、その場その場でストーリーを書き上げた。うまくいったら、それをベースにする。ダメだったらやり直す。どんな趣味でも同じだと思うけどね…。
あれ、今のアーノルドか? 通り過ぎて行ったのは?(※この時、インタビューを行っていたレストランの窓の外をアーノルド・シュワルツェネッガーが通り過ぎる)彼はかっこいいね。…話を戻すけど、周りの若者がサーフィンをしていた時に、私たちは映画を撮っていたんだ。結構クールだったよ。
――以前ショーン・ペンにトム・クルーズと共演した『タップス』(1981年)の思い出を尋ねたら、「トムはいい人すぎるから、絶対に成功しないと思っていた」と言っていました。
トムは本当にいい人だよ。トムと兄のエミリオがオーディションを受け、『アウトサイダー』(1983年)の準備をしていた時、トムは私たちの実家にしばらく泊まっていたんだけど、最高だった。
――トムはあっという間にスターになりましたね。そういう風に見えましたか?
トムにはスターの素質があった。女性は彼のそばにいたいと思うし、男性は彼のようになりたいと思う。彼には純粋さもあった。だから、彼のような凄い才能が現れた時、人々は意表を突かれたんだと思う。多才なトムに人々は突然、嬉しい驚きを覚えたんだろう。彼がいまや完璧なアクションスターになっていることは知っているが、一方でアカデミー賞に値するような素晴らしい演技も見せている。『ザ・エージェント』『7月4日に生まれて』『マグノリア』だ。あ、ごめん。4つだ。『レインマン』もだ。多分5本目もあるんだけど、思い出せないな。
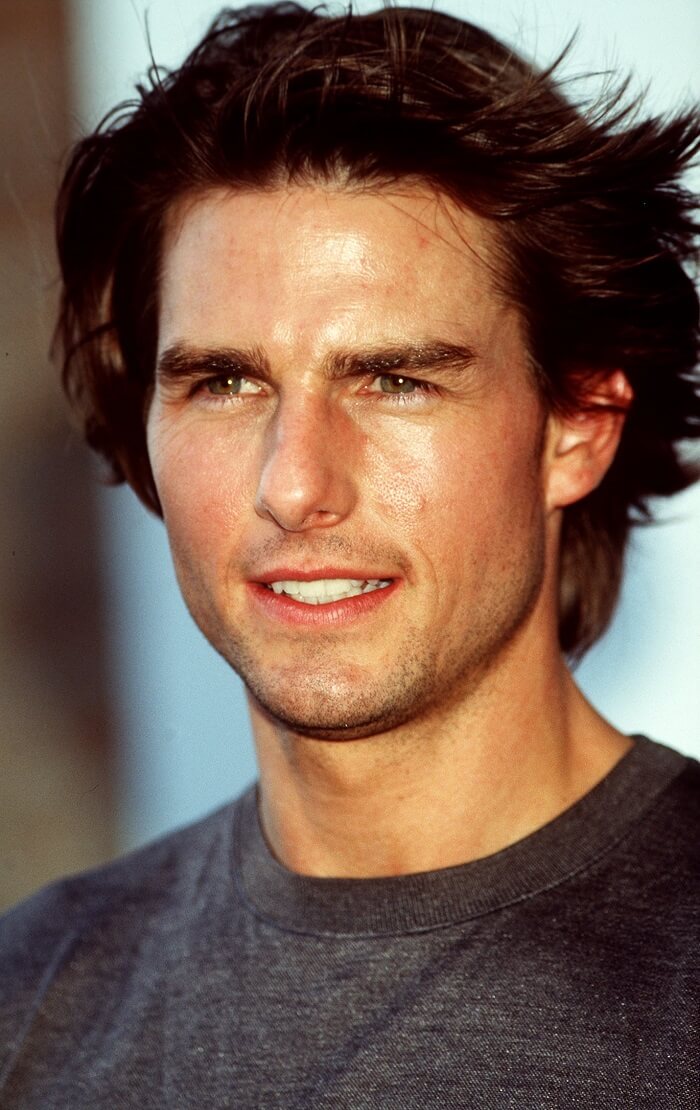
トム・クルーズ
――トムが『卒業白書』に主演したのは1983年ですが、同世代の彼の活躍に焦りを感じましたか?
15歳の時にセラピストと出会うという恩恵を得られた。15歳でセラピーを受けたい人なんている?(笑) その人とのあるセッションを覚えているよ。当時の私はまだ演技もしていなかったし、16歳くらいだった。セラピストから「他人の成功を祝わない限り、自分が成功を手にすることはできない」と言われて“ああ、そうか”と思った。彼とのセッションで覚えているのはそれだけ。だからみんなのことを応援していた。苦しくはなかったよ。実力主義の時代だったし、みんなに行き渡るくらい多くの仕事があると感じていたから。
オリヴァー・ストーンに見出されて
――ジョン・ヒューズ監督の映画の主役に挑戦したことはありますか?
いや、オーディションは受けたことがない。高校生の時、兄のエミリオが主演したヒューズ監督の『ブレックファスト・クラブ』(1985年)の試写会に誘われたんだ。素晴らしい映画だ。ヒューズ監督は『若き勇者たち』(1984年)で私とジェニファー・グレイが仕事をしたことを知っていた。そしてジェニファーと私は『フェリスはある朝突然に』(1986年)に起用されたんだ。
――主人公を演じた『プラトーン』の時はどうでしたか?
39年ほど前の話だけど、あの役は人生を変えるものだった。オーディションを受けたり、受けなかったりする日々の中、目標やプロセス、準備の仕方は何も変わらないけど、だんだん楽しくなるんだ。突然人から感謝されたりしてね。『プラトーン』は、一夜にして私の人生のすべてを変えた。
――ジャングルの中で爆撃シーンもあるような撮影でしたが、一番大変だったことは何ですか?
持久力が必要だった。台詞を覚えるのにはそんなに時間はかからなかったけど、ものすごく感情的になる場面がいくつかあり、そういう感情の中に入ろうとした。悲しくなるフリだったとしても、実際本当に悲しくなって、そう演技することができたんだ。

2006年のカンヌ映画祭で『プラトーン』のオリヴァー・ストーン監督、ウィレム・デフォー、トム・ベレンジャーと再会
――監督のオリヴァー・ストーンはどうやって、それまで青春映画に出ていたあなたから『プラトーン』のような演技を引き出したのですか? 監督は明らかに、望んでいたものを作り上げたように思いますが。
まだトレーニングキャンプにいた時に、キャスト全員で読み合わせをした。それを通して、監督は、実際の撮影以外で皆がどこまでやるかを見ることができたんだ。彼が体験したことを演じる役回りの私は、彼に誇りに思ってもらいたかった。まず彼を喜ばせたかったし、次に私自身を喜ばせたかった。複雑なシーンがいくつもあり、監督が身体で反応しているのが視界の端に映った。彼はとても興奮していたよ。残り1分で5点差を追うお気に入りのチームを応援しているような感じでね。あの映画の撮影中は、やり遂げた満足感と幸福感に満ちて家路についた夜が何度もあった。自分のやったことで監督がそう思ってくれたようだったからね。
でも私たちは若かったからいろいろ大変だった。スピーチする時、セットに行く時、帰る時、そういうのも演技のうちに入るし、誤魔化していくゲームみたいなものだった。『プラトーン』での私たちは精神的につながっていたから、(ストーン監督と再び組んだ1987年の)『ウォール街』でも友情、つながりにまで波及していれば良かったのにと思うよ。
――『ウォール街』はどう違ったのですか?
全然違った。あれは本当に難しい撮影で、ある意味『プラトーン』よりも難しかった。対話の量やロケの量が凄かったし、『プラトーン』がアカデミー賞の作品賞や監督賞を獲ったことで、監督が自分に課したプレッシャーの量もすさまじかった。細部にまでエネルギーが宿っていた。マイケル・ダグラスと私のキャラクターが出会うシーンは2日間かけて撮影し、2日間で56回撮影した。マイケルと知り合ってから一週間が経った頃、彼が「何かほかのアイデアはあるか? もう思いつかない」と言っていたんだ。私ももう限界に来ていて、「ないです!」という感じだった。さらに、全米監督組合(DGA)のストライキが行われることになったため、撮影の終盤は8日間で16日間分の撮影をこなさなければならなかった。半分の時間で 2 倍の作業を行う必要があったんだ。私とマイケルはそうした苦労を通じて絆を深めたよ。
――マイケルも俳優一家の出身ですね。
自分がずっと見て育った人や憧れの人には、無視できないような神秘的な雰囲気がある。(映画『JAWS/ジョーズ』の主演)ロイ・シャイダーに会ったようなものだよ。1975年の夏、その後の私の人生を永遠に変えることになった、10歳の頃に観た『ジョーズ』の世界に引き戻されるんだ。
シャイダーについては後悔していることがある。12歳の時の私は『ジョーズ』を50、60回は観たくらいに執着していた。ある日、父が郵便局で用を足す間、私は今ではもうないマリブのダイナーで父を待っていた。するとすぐ隣に人影を感じたのでチラッと見たら、『ジョーズ』でブロディ署長を演じたロイ・シャイダーがいた。私は驚きのあまり固まった。「すみません、シャイダーさん、私の父はマーティン・シーンです。父とは多分ニューヨークで会ったことがありますよね。父は今、通りの向こう側にいます。ただご挨拶がしたかっただけです」と言えれば良かったのに、一言も発することができなかった。彼はたしかコーヒーを飲んでいただけで、間もなく出て行ってしまい、その後で父が戻ってきた。父があと一分早く戻っていたら、「やあ、ロイ。これは息子だ」と言ってくれただろうに。私は何年も何年もこの時のことを覚えていた。
『ハーパー★ボーイズ』で私の母を演じたホランド・テイラーはロイととても仲が良いので、私がその話をするとロイ本人に伝えてくれたんだ。彼はそれを聞いて喜んでくれたそうだよ。また後悔の話になるけど、私はロイに何年も連絡を取ろうと思ったけど、結局一度も連絡しなかったんだ(※ロイ・シャイダーは2008年に死去)。
――今後もシットコムに出演したいですか?
そうだね。とても楽しいだろうね。視聴者も楽しめると思う。
――ロリーとまた一緒にやってみたいと思いますか?
もちろん。もし彼が「始めたことを最後まできちんと終わらせよう」と言ったら応じるよ。台本が届いたら読む。なぜなら、それが皆の望むものだから。道で私に近づいてきて、「重厚なドラマに出てほしい」なんて言う人は誰もいない。世の中の雰囲気に基づいてそう考えているだけなんだけどね。実際に出会った人たちは、『ハーパー★ボーイズ』や『メジャーリーグ』『ホット・ショット』『メン・アット・ワーク』といったコメディ作品について話したがるんだ。

『ハーパー★ボーイズ』
――きちんと復帰できたこと、心配する必要がないことを証明したいですよね。成功するには規律が必要です。
ありがとう。それが『Bookie』をやる上で重要なことだった。責任、プロフェッショナリズムを問うオーディションだった。私はいつも最初に現場に到着し、最後に帰る男だった。 過剰な準備をして臨んでしまった…。
――そんな男にまたなりたいですか?
そうだね。またそうなりたい。私は求められたことをやり、できるということを証明するためにそこにいた。チャックは俳優に好きに演技させるタイプで、だからこそ素晴らしい作品を創り続けてきた。そして彼はいつも正しい。認めるのはシャクだけど、彼はいつも正しい。どうしてかつての私はそのことを見逃していたのか? でも、『Bookie』の現場では以前のようなエネルギーを再び感じることができた。とても刺激的だったよ。
そういえば、(製作会社である)ワーナー・ブラザースの敷地にある巨大スクリーンでキャスト、スタッフと一緒に『Bookie』を見た。38ページ目のシーンはかなりうまくやれたと思う。番組は素晴らしかった。でも、ほかの俳優たちがあることにすごく注目していたんだ。
――何ですか?
私の身体のある部分で、修正する必要があると思った。私の首だよ。体重の重い人が減量した時、七面鳥をむさぼり食うような状態になっているように見えるものが首にあったんだ。垂れ下がった、パタパタした部分。これに気づいたのは月曜日の夜で、火曜日の朝に医師に電話をしたよ。手術するか、タートルネックを買いに行くかのどちらかだったからね。でも、あんな自分の姿はもう見たくなかった。誰もあれは見るべきではない。10年間カメラに映らなかったことのデメリットだね。毎日鏡で自分の姿を見て、“いい感じだ”と思ってその日をスタートさせるから、この首はなんとかしないといけないと思ったんだ。
――そのようなものをなくそうとするのは虚栄心でしょうか?
私は身体の中には何も埋め込まない。表面を綺麗にスムーズにするだけだよ。どうしても気になったからね。
――『Bookie』はスポーツ賭博に関する話ですが、あなた自身は賭け事は好きですか?
やらない。以前はそういう世界にいたけど、2009年にやめたよ。勝っても何も感じなくなった時に、“これは終わりだ”となったんだ。ギャンブル依存症ではなかった。一度お金を借りなければならなかったが、それは私にとって一線を越えたことだった。私が常に守っていたルールは、負けた場合に払えないような賭けはしないということだったからね。賭け金は多かった。数週間分の給料に値する金額だったな。『ハーパー★ボーイズ』のプロデューサーの一人が私のギャンブルのパートナーだった。あるシーンを撮っていた時、賭けている試合のスコアを追うことができなかった。クリエイターのリー(・アロンソーン)やチャック、数人のライターと一緒にあるシーンを修正しようとしていた時、そこにいた一人の男(ギャンブルのパートナー)は私の視界の端で、試合の経過に応じて親指を立てたり親指を下げたりしていた。結局その賭けには負けてしまい、撮影を続けるために興奮を装いながら演じなければいけなかった。
――『ハーパー★ボーイズ』が大好きだったので、チャーリー・ハーパーが見られなくなって寂しいです。
ありがとう。私もしばらくの間、あのキャラクターと別れて寂しかったよ。
(翻訳/Erina Austen)






