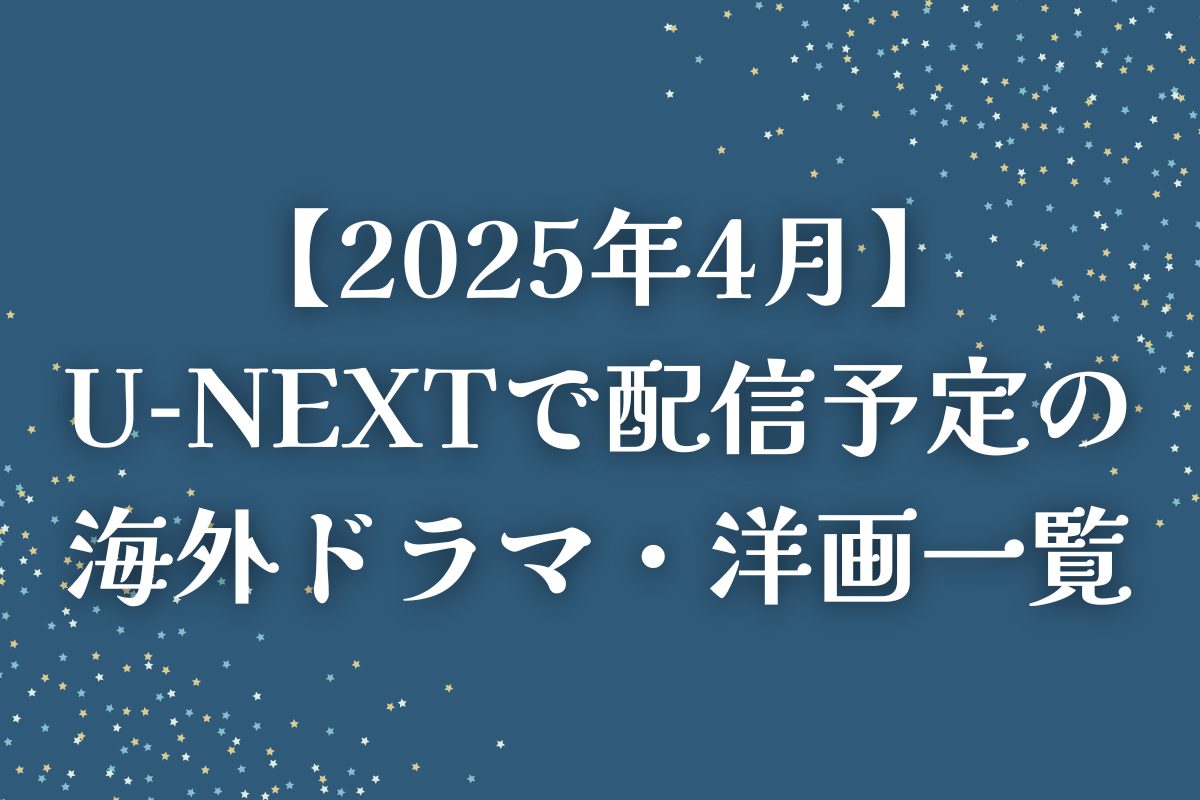ペットとして、いや家族として、我々の暮らしの中に当たり前のように存在するネコ。そのきっかけを作ってくれた画家の半生を描いた映画『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』が12月1日(木)より公開となる。傑作ドラマ『ランドスケーパーズ 秘密の庭』の俊英ウィル・シャープ監督のもと、ベネディクト・カンバーバッチ(『SHERLOCK/シャーロック』)とクレア・フォイ(『ザ・クラウン』)が夫婦役を務めるという海外ドラマファンにはたまらない配役もさることながら、ネコカフェまである今の時代の礎となった当時の奮闘を描いている点からも必見作としてお薦めしたい。【映画レビュー】
映画『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』あらすじ
イギリスの上流階級に生まれ、父亡きあと一家を支えるためにイラストレーターとして日々奮闘するルイス(ベネディクト)は、ある日、妹の家庭教師としてやってきたエミリー(クレア)に好意を持ち、恋に落ちる。「身分違いだ!」と猛反対する周囲を押し切り、二人は結婚するが、幸せな日々も束の間、エミリーは末期ガンを宣告され、二人は失意の底に…。そんな悲しみの中、庭に迷い込んだ子猫を保護した二人は、彼にピーターと名付け、残された時間を“3人”で慈しむように過ごしていく。
「つらくても描き続けて」妻の最後の言葉が胸に響く
ルイスとエミリーの悲しい別れをまるで察知したかのように、突然、救世主のように現れた子猫のピーター。エミリー亡きあと、ルイスは彼を心の友とし、ネコの絵を猛然と描き続け大成功を手にする。「つらいことばかりでも、世界は美しさで満ちている。どんなに悲しくても描き続けて…」というエミリーの最後の言葉を追いかけるように、ルイスはネコを描いて、描いて、描きまくる。この一心不乱の創作活動が名画を次々と生み出し、それまで不吉な存在として恐れられていたネコのイメージを一変させ、その魅力に人々が気づき始める大きなきっかけを与えていく。まさに悲しみと喜びは表裏一体、「何があっても描き続けて」というエミリーの言葉の意味が、終盤にさしかかるにつれて心にジワジワと響いてくる。

当然、本編にはいろんなネコが大挙登場するが、こんなに愛らしい動物の魅力に気づかないなんて、よほど迷信が人々の心を呪縛していたんだなと痛感する。ルイスが生きた19世紀末から20世紀初頭、ネコは魔術や罪と同類と見られ、蔑まされていた時代。それがペットとして受け入れられ、文豪・夏目漱石(「吾輩は猫である」に登場する絵葉書の作者だとも言われている)にインスピレーションを与え、SFの巨匠H・G・ウェルズにも絶賛される存在に。
今ではネコカフェなんかも登場し、我々人間社会の中にすっかり溶け込んでいるが、このネコと人間が共存する平和な世界を俯瞰すると、改めてルイスに敬意を表したい気持ちになる。ただ、ルイス本人は、ネコを救おうという気持ちではなく、迷信や社会の偏見に囚われず、つねにピュアな心でネコの本質を見ていただけ。身分違いと言われたエミリーと愛を貫くことができたのも、彼女の外側ではなく本質を愛したから。本質を見ることがいかに社会を健全にするかが学びとれる。
それにしても、ベネディクトとクレアの演技が素晴らしい。コミュ障で不器用だけれど、純粋で愛情深い“風変り”な画家ルイスにベネディクトは命を吹き込み、そんな彼を亡くなったあとも美しい思い出と思慮深い言葉で励まし続けるエミリーに包容力をもたらしたクレア。子猫のピーターとともに愛を育むあの束の間の時間がとてもいとおしく、今、思い出すだけで涙が止まらない。

愛に溢れた夫婦が無邪気なネコと戯れている…ただそれだけのシーンに感情が動くのは、背景に劇的物語があることはもとより、そこに映画という作り物を超えた“本質”があるからだ。世界は美しい…それは案外、身近なところに輝いているものだったりするのかも。
映画『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』は、12月1日(木)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国ロードショー。
(文/坂田正樹)
Photo:『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』©2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 提供:木下グループ 配給:キノフィルムズ